
「ばあちゃん、伊波礼毘古(いわれびこ)が伊須気余理比売(いすけよりひめ)と結婚した話、詳しく教えて!」



「その話な、伊波礼毘古が日向(ひむか)におったとき、阿多(あた)の小椅君(おばしのきみ)の妹、阿比良比売(あひらひめ)と結婚して、二人の子どもが生まれたんや。」



「その子どもたちの名前は?」



「多芸志美美(たぎしみみ)と岐須美美(きすみみ)やったんやけど、伊波礼毘古はさらに皇后となる少女を探してたんや。」



「で、その少女って誰なん?」



「大久米(おおくめ)が言うには、三島の湟咋(みぞくい)の娘で、勢夜陀多良比売(せやだたらひめ)という美しい少女がいて、その少女が大便をするとき、丹塗りの矢が流れてきて、その少女の陰部を突いたんや。それで、その少女は驚いて慌てふためいたんや。」



「その矢がな、立派な男性に変わって、その少女と結婚したんや。その男性が富登多多良須須岐比売(ほとたたらいすすきひめ)で、後に比売多多良伊須気余理比売(ひめたたらいすけよりひめ)と名乗ったんや。」



「その伊須気余理比売がどうやって天皇に選ばれたん?」



「七人の少女が高佐士野(たかさじの)で野遊びしてたとき、大久米が伊須気余理比売を見て、天皇に歌で知らせたんや。」



「その歌はこうやったんや。」



「大和の高佐士野(たかさじの)を七人行く少女たちよ、その中の誰を妻としようか。」



「伊須気余理比売がどうやって選ばれたん?」



「伊須気余理比売がその少女たちの先頭に立ってたから、天皇はその少女を一番先に立ってると知って、歌でお答えになったんや。」



「ともかくも一番先に立っている、年上の少女を妻としよう。」



「それで、大久米が伊須気余理比売に天皇の言葉を伝えたんやな?」



「そうや。伊須気余理比売はその言葉を聞いて、歌で返事をしたんや。」



「それは、どんな歌やったん?」



「あま鳥、つつ、千鳥、しととのように、どうして目じりに入墨をして、鋭い目をしているのですか。」



「大久米はどう答えたん?」



「大久米は歌でこう答えたんや。」



「お嬢さんにじかにお逢いしたいと思って、私は入墨をしてこんなに鋭い目をしているのです。」



「こうして伊須気余理比売は天皇に『お仕えいたしましょう』と答えたんや。その家は狭井河(さいかわ)のほとりにあって、天皇はその家に一夜お休みになったんや。」



「狭井河の名前の由来は?」



「狭井河のほとりには山百合(やまゆり)がたくさん生えていて、その山百合の草の名を取って狭井河(さいかわ)と名づけられたんや。」



「その後、どうなったん?」



「伊須気余理比売が宮中に参内したとき、天皇が歌ったんや。」



「葦原(あしはら)の中の荒れたきたない小屋に、菅(すが)の畳を清らかに敷きつめて、私たちは二人で寝たことだ。」



「それで生まれた子どもたちは?」



「日子八井(ひこやゐ)、神八井耳(かむやゐみみ)、神沼河耳(かむぬなかわみみ)の三柱やったんや。」
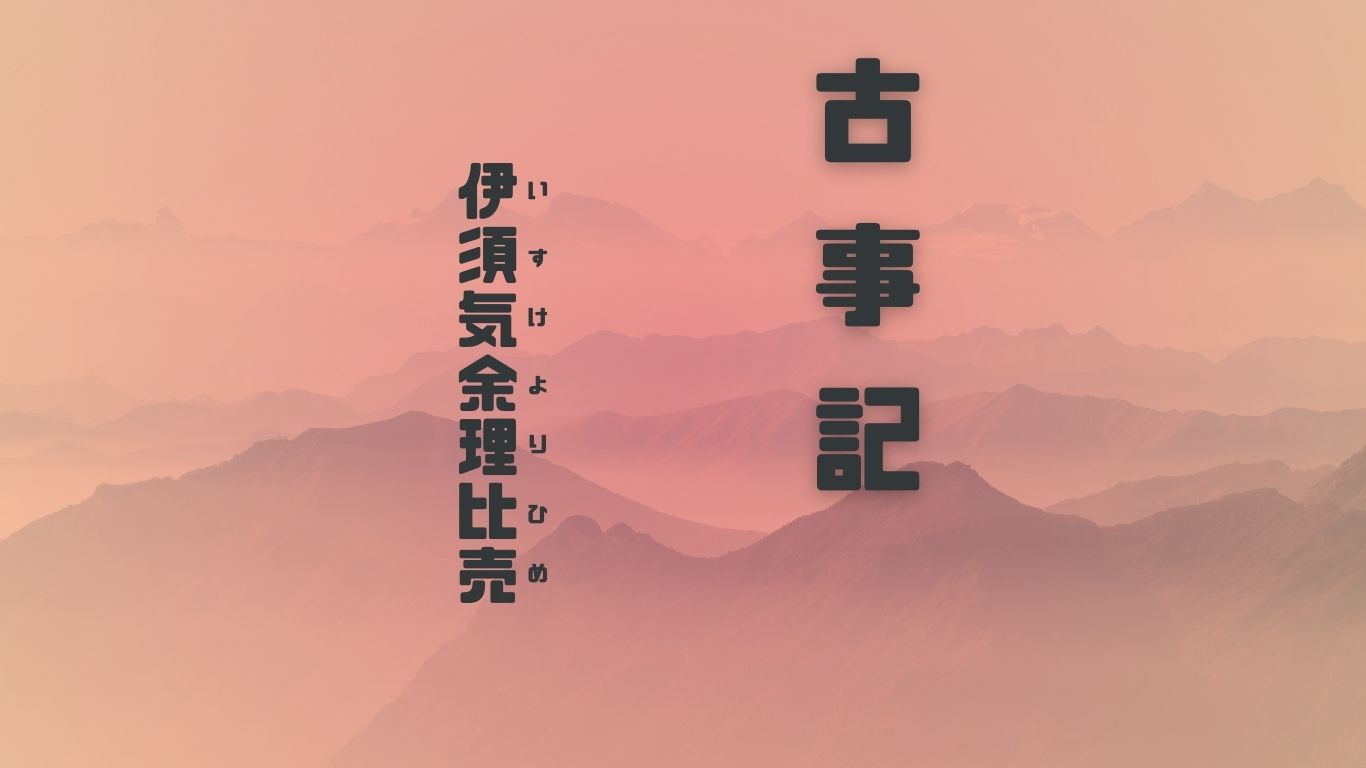

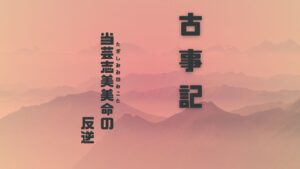
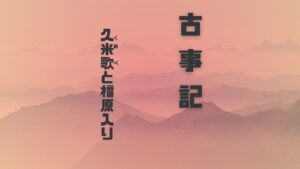

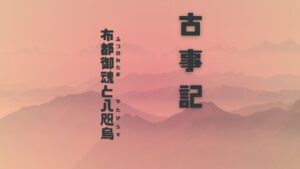
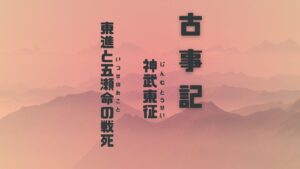
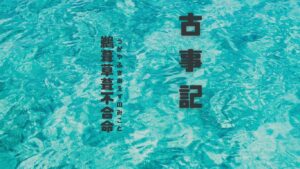
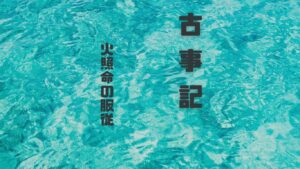
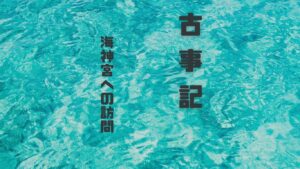
コメント