
「ばあちゃん、神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこ)と五瀬命(いつせのみこと)はどうしたん?」



「うん、二人は高千穂宮におったんやけど、どこに行ったら天下を安定させられるか相談したんや。それで、東の方に都を求めて出発することにしたんや。」



「それで、どこに行ったん?」



「日向(ひむか)から筑紫国(つくしのくに)へ向かったんや。宇沙都比古(うさつひこ)と宇沙都比売(うさつひめ)という人たちが、足一騰宮(あしひとつあがりのみや)を作っておもてなしをしてくれたんや。」



「筑紫国の次は?」



「筑紫国からさらに岡田宮(おかだのみや)に一年滞在して、その後、安芸国(あきのくに)の多祁理宮(たけりのみや)に七年間滞在したんや。」



「長い間いたんやなぁ。」



「うん、その後、吉備(きび)の高島宮(たかしまのみや)に八年間滞在して、その国から進むと、亀の甲に乗った者がやってきたんや。」



「亀の甲に乗った者?それは誰やったん?」



「その者は国つ神(くにつかみ)で、海路をよく知ってる言うたんや。それで、火遠理命(ほおりのみこと)に従うことになったんや。」



「その後どうしたん?」



「五瀬命は、浪速渡(なみはやのわたり)を経て白肩津(しらかたのつ)に船を停めたんや。その時、登美毘古(とみびこ)が軍勢を起こして待ち受けてたんや。」



「それで、どうなったん?」



「戦いになって、五瀬命は登美毘古(那賀須泥毘古)が放った矢を受けてしまったんや。五瀬命は、『日の神の子として、日向きで戦うのは良くなかった』と感じたんや。」



「それで、どうしたん?」



「五瀬命は南から回って進んで、血沼海(ちぬのうみ)で手の血を洗ったんや。その海を『血沼海』と名付けたんや。」



「その後、紀伊国(きいのくに)にはどう行ったん?」



「紀伊国の男之水門(おのみなと)に至って、戦いの傷を振り返りながら死んでしまったんや。だから、その水門は『男の水門』と名付けられたんや。」



「五瀬命の御陵はどこにあるん?」



「紀伊国の竈山(かまやま)にあるんやで。彼の死後、その地域では彼の名が伝えられ、敬われてるんや。」
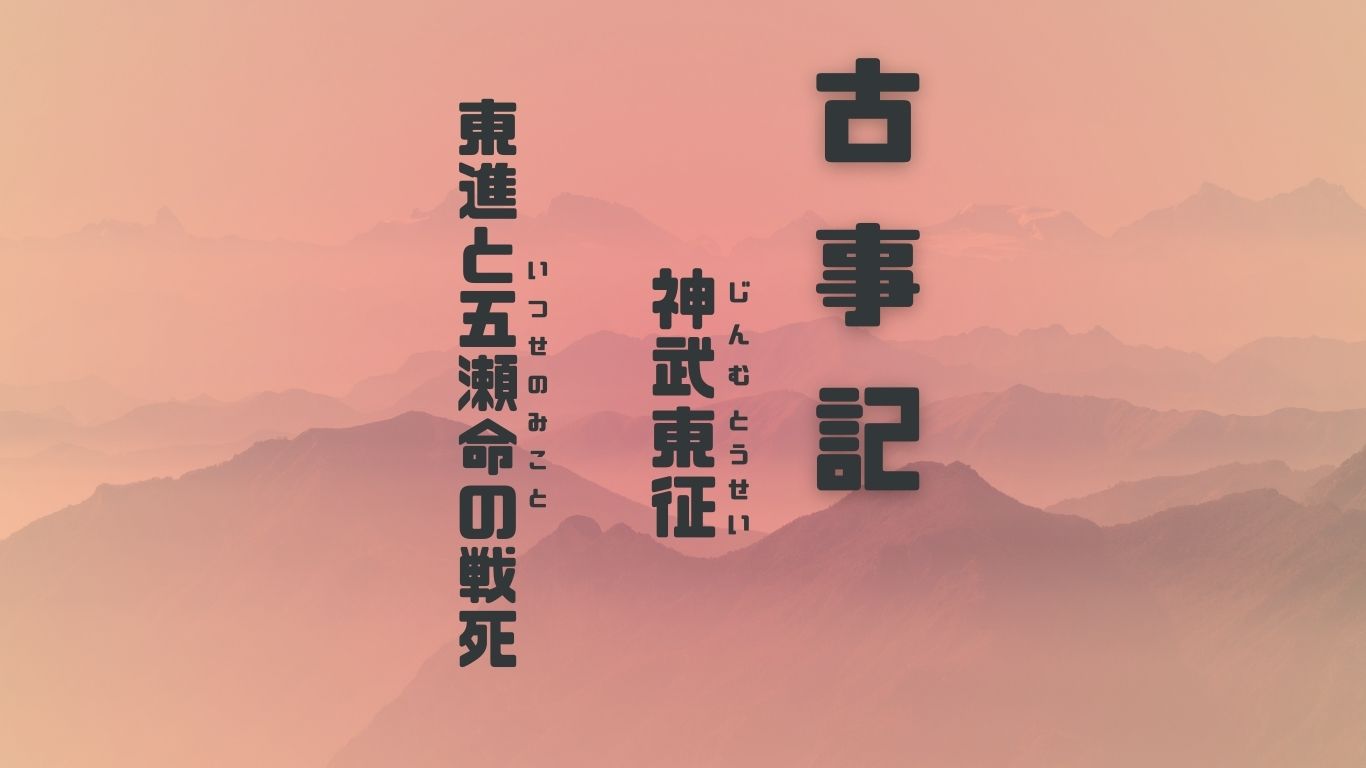

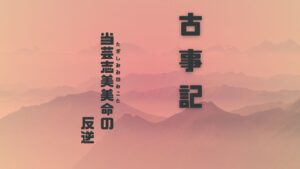
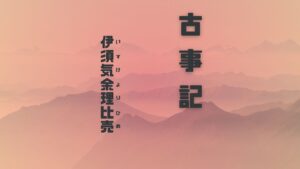
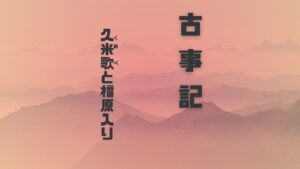

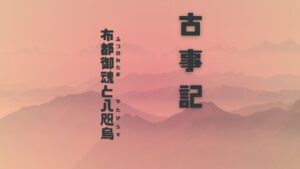
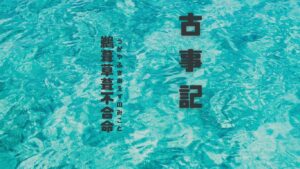
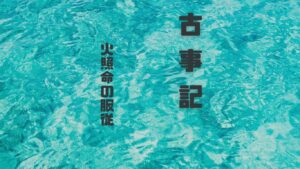
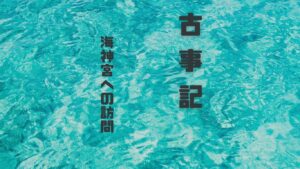
コメント